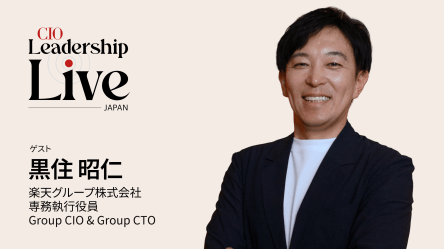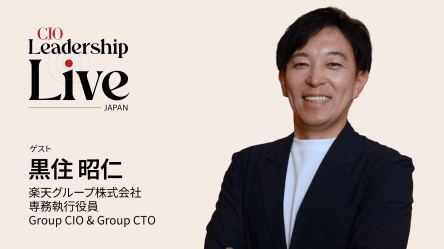静岡県では現在、地方発のデジタル変革(DX)を本格的に推進する「ふじのくにDX推進計画」のもと、企業・自治体・教育機関が一体となって未来の地域社会を描いている。その中で、県内企業のDX支援に乗り出したのが鈴与グループのIT中核企業、鈴与システムテクノロジーだ。静岡県におけるDXの課題とは何か。県内企業にDXを浸透させるにはどうすればよいのか。社長に話を聞いた。

人口減少が引き金となった静岡県のDX戦略
日本列島のほぼ中央に位置する静岡県は、東西を結ぶ交通の要衝として発展してきた。陸路では東海道新幹線、東名高速道路、国道1号線が、海路では水深2,550mを誇る清水港が物流の大動脈として機能し、製造品出荷額で全国3位(2020年工業統計調査)を記録する“ものづくり県”として知られている。
しかし、静岡県も御多分にもれず、2007年12月の378万人をピークに人口は減少傾向にあり、2025年6月には349万人にまで減少している。外国人の転入が増加する一方で、自然減と若者の首都圏への流出が人口減少を加速させている。
若者が県外に流出する主な理由は、雇用の質と生活の利便性における格差だ。都市部に比べて交通・娯楽・教育・医療などの生活インフラが整っておらず、賃金や安定性、やりがいのある企業も少ない。地元に希望する大学・学部がないため、進学時点で県外に出るケースも多い。
この若者流出は単なる人口減少にとどまらず、労働力人口の減少、消費市場の縮小、税収減による行政サービスの低下といった「負のスパイラル」を引き起こしている。
こうした状況を受けて、静岡県庁は移住・定住の促進と多様性ある地域社会の実現を目指し、2022年度から2025年度にかけて「ふじのくにDX推進計画」を立ち上げた。
この計画では、県庁・市町・地域社会の3つのフィールドで以下の5つの政策を展開している:
- デジタルデバイド対策の実施
- 超スマート社会実現に向けた環境整備
- デジタル技術の実装促進
- 新しい生活様式への対応
- データ分析・利活用の推進
10年後には「いつでもどこでも必要なものやサービスを受けられる、豊かで持続可能な社会」の実現を目指している。
静岡県庁経済産業部産業政策課の石川智久産業政策班長はこう語る:
「県内企業のDXにも力を入れています。IT人材の不足を補うため、SHIZUOKA INNOVATION PLATFORM(SHIP)でセミナーを開催し、社内DXを推進する人材育成に取り組んでいます。静岡工科短期大学では、ものづくりに必要なデジタル技術を学べる環境も整えています。県庁だけでは限界があるため、商工会議所や産業振興財団など産官学が連携し、静岡県AI・IoT導入推進コンソーシアムなどを展開しています」
中小企業DXの壁──人材・資金・意識の三重苦
そうした中で県内企業のDX支援に乗り出したのが鈴与グループのIT中核企業、鈴与システムテクノロジーだ。鈴与グループは1801年に清水湊の特許問屋として創業した老舗企業であり、現在は倉庫事業を中心に多角的に展開。グループ140社のDXなどを担ってきたのが鈴与システムテクノロジーだ。
2024年に社長に就任した林田敏之氏は、NTTデータやNetyearGroupでのDX支援経験を持ち、静岡でのDXに新たな視点を持ち込んだ。
「静岡県の人口は2007年をピークに減少し、2024年には減少幅が最大となりました。若者の県外流出も平均の2倍以上です。『静岡を日本のデジタル化の先駆けにする』というビジョンのもと、地域から新たな価値を創出し、若者が働きたいと思える企業を増やしたいと考えています」
林田氏は、静岡県のDXが全国平均から見ても遅れていると指摘する。帝国データバンクの調査(2023年7月)によれば、DXに対応済の県内企業は19.8%。売上10億円未満の企業ではわずか10.8%にすぎない。県内企業の99%が中小企業であることも、DX推進の難しさに拍車をかけている。
「IT化やDXに関する“ふわっとした困りごと”を抱えていても、社内に詳しい人材や相談先がない企業が多い。資金面の制約も大きく、首都圏のベンダーは価格的に頼みにくい。地元ベンダーも支援体制が限定的で、上流から下流まで一気通貫で対応できる企業が少ないのです」(林田氏)
鈴与システムテクノロジーでは、DXの第一歩を支援するために、無料相談窓口の設置や「デジタル診断」サービスの開発を進めている。
「まずは自社のデジタル化の進捗を可視化することが重要です。人材が不足している企業には、われわれがシステム開発を請け負う仕組みも検討しています。紙の業務をデジタル化することが、DXの入り口になると考えています」(林田氏)
中小企業では、機密情報から販売情報までをExcelで一元管理する“エクセルのお化け”が蔓延しており、業務効率化の妨げとなっている。
「中小企業は資金的に余裕がなく、1件10万〜20万円の案件ではIT企業が手を出しづらい。だからこそ、課題をパターン化し、ソリューションとして提供することが必要です」(林田氏)
成功モデルの創出と社内意識の統一
静岡県のデジタルトランスフォーメーション(DX)において、現在最も大きな課題の一つは「成功モデルの不在」である。
林田氏は次のように語る。
「地元企業からは『成功モデルがない』という声が多く聞かれます。『こういう取り組みをして売上が伸びた』という具体的な事例が少しでもあれば、それに続く企業が出てくるはずです。しかし、そうした事例が表に出てこないのが現状です。県内企業の多くは、自社のデジタル化の進捗状況を正確に把握できていません。社内に多少詳しい人がいると、それだけで“最適化されている”と誤認してしまうケースもあります。実際には、より高度な取り組みが求められているにもかかわらず、その必要性に気づけていないのです。そこで、デジタル診断などを活用し、『他社はここまで進んでいます』という客観的な指標を示すことが重要だと考えています」
また、静岡県内のDX推進を阻む要因として、「社内の抵抗」が挙げられる。これにどう対応すべきか。
「ある特殊車両の点検を行う企業では、社長が以前から社内改革を望んでいましたが、現場の抵抗が強く、なかなか進みませんでした。そこで弊社の社員を現場に派遣し、ヒアリングを重ねながら地道に通い、信頼関係を築いていきました」
林田氏は、この取り組みを通じて「現場との一体感を醸成し、社長のビジョンを浸透させることの重要性を改めて実感した」と語る。
「これまで弊社では、勤怠管理、ワークフロー、旅費精算、BIツール、RPA、M365の活用など、さまざまなDX施策を実施してきました。最も困難だったのは、『なぜDXを進めるのか』『どんな成果が得られるのか』という点について、組織内で納得感を得ることでした。経営層と現場が同じ言語で対話し、共通のゴールを認識することが、DXの成否を分ける鍵だと感じています。社内の意識が揃えば、取り組みの質とスピードは大きく向上します」
地域連携がDX推進のカギ
静岡県は、富士川以東の東部(三島・伊東・熱海などの観光地)、静岡市を中心とする中部(農業・中小製造業)、浜松を中心とする西部(自動車・楽器などの大手企業)という三つの地域に分かれており、それぞれが独自の産業構造を持つ。そのため、県全体での連携が取りづらいという課題がある。
「三地域は必ずしも連動していません。だからこそ、清水市出身の弊社だけでなく、他の企業も巻き込み、静岡県全体のDXを広げていきたいと考えています。地元の複数の有力企業と連携できるようなスキームを構築したいと思っています」
さらに、鈴与グループの鈴与商事(エネルギー系企業、約5,000社の取引先)にもアプローチを開始。グループ内の静岡理工科大学との産学連携も視野に入れている。
「ただし、単なる産学連携ではなく、地域社会との連携を強化したいと考えています。DXとは直接関係ありませんが、毎週木曜日に学生と社会人を招いた勉強会を開催しており、これを通じて静岡県全体のムーブメントにつなげていきたいと思っています」
最後に、静岡県庁の石川氏は今後の展望についてこう語る。
「AIひとつとっても、県庁だけでは対応しきれない部分があります。今後は県内外の民間事業者とも連携しながら、DXを推進していきたいと考えています」