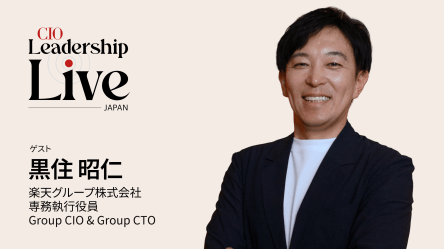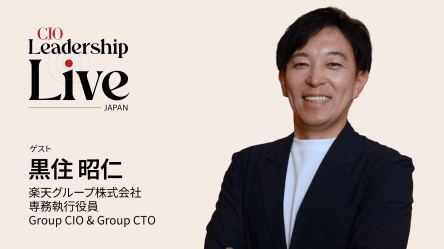日本国内の市場縮小と深刻化するIT人材不足を背景に、日本企業のエンジニア組織において英語を公用語とする動きが加速している。2010年の楽天による大胆な宣言を皮切りに、多くの企業がグローバル競争を勝ち抜くための生存戦略として英語化に着手した。しかし、その道のりは決して平坦ではなく、トップダウンの急進的な改革が現場の混乱を招いた事例も少なくない。本記事では、過去10年以上にわたる日本企業のエンジニア組織における英語化の軌跡をたどり、その目的、導入プロセスの変遷、直面する課題とそれを乗り越えるための工夫を、成功・失敗事例を交えながら多角的に分析する。

日本企業、特にエンジニア組織における英語公用語化の動きは、2010年に楽天とファーストリテイリング(ユニクロ)が相次いで宣言したことを契機に本格的な潮流となった。この動きは単なる一過性のブームに終わらず、英語化に踏み出す企業は増加傾向にあり、特にIT業界では導入事例が目立っている。この背景には、日本が直面する構造的な課題、すなわち少子高齢化による国内市場の縮小と、それに伴う海外市場への進出の必要性がある。グローバルな事業展開を推進する上で、海外拠点との円滑な情報共有や現地のビジネスを加速させるためには、英語という共通言語が不可欠となる。楽天の三木谷浩史会長兼社長が後に「英語を社内公用語にしなければ、楽天は終わっていたかもしれない」と振り返ったように、英語化は旧来の日本的な企業風土を打破し、ダイバーシティを推進することでグローバル企業へと変革するための核心的な戦略と位置づけられている。
もう一つの大きな動機は、深刻なエンジニア不足を解消するための、優秀なグローバル人材の獲得競争である。国内だけで有能な人材を確保することが困難になる中、採用の視野を世界に広げる必要に迫られている。「日本語ができない」という理由だけで優秀なエンジニアの採用を断念するのは、企業にとって大きな機会損失に他ならない。この問題意識から、日本語能力を問わずに働ける環境を整備することで、世界中の人材プールにアクセスしようという狙いがある。実際に、英語化を推進したメルカリではエンジニアの約40%が外国籍であり、マネーフォワードでも30カ国以上から集まったエンジニアが全体の4割超を占めるなど、英語化が多国籍チームの編成とグローバル採用の拡大に直接的に結びついている事実は見逃せない。
さらに、組織全体の生産性向上とイノベーション創出という目的も存在する。英語を共通言語とすることで、国籍や拠点に関わらず情報共有がスムーズになり、組織全体の意思疎通の効率が高まる。そして、多様な文化的背景を持つ人材が協働する環境は、単一文化の組織では生まれにくい新たな視点やアイデアを誘発し、イノベーションの土壌を育むと期待されている。これは単に外国人を採用するという次元の話ではなく、言語の壁を取り払うことで「インクルーシブな多言語環境」を構築し、組織の創造性と活力を維持するための能動的な取り組みなのである。こうした戦略的な目的意識のもと、例えば資生堂は2018年に本社の社内公用語を英語にしており、そのほかにも英語活用を積極的に拡大する企業は複数存在する。リモートワークの普及や高度専門職ビザの要件緩和といった外部環境の変化も、この流れをさらに後押ししている。
導入アプローチの変遷:全社一斉型から段階的・実践重視型へ
英語公用語化の導入プロセスは、企業によって様々であるが、そのアプローチは大きく二つに大別できる。一つはトップダウンで全社一斉に導入するモデルであり、もう一つは特定の部門やチームから段階的に導入し、徐々に範囲を拡大していくモデルである。初期には前者の大胆なアプローチが注目されたが、近年では後者の「現実的な部分英語化」が主流となりつつある。
全社一斉のトップダウン型英語化の典型例が、先駆者である楽天だ。2010年、三木谷氏が年頭方針として英語公用語化を宣言し、約2年間の移行期間を経て、2012年には会議や社内資料、メールに至るまで全てを英語に切り替えた。さらに、昇進要件にTOEICの基準スコアを設けるなど、人事評価制度とも連動させることで、施策を強力に推進した。その結果、社員の平均TOEICスコアは830点台(2018年時点)に達し、外国籍社員の比率は全社員の20%に達した。特に新規採用のエンジニアにおいては、実に7割から8割が外国籍となり、目覚ましい組織のグローバル化を果たした。
しかし、こうした急進的な全社一斉型は、社員に短期間での言語転換を強いるため、大きな混乱や反発を生むリスクも内包している。同時期に英語化を掲げたユニクロの事例は、その難しさを示す教訓となった。同社もまたトップダウンで本社会議の英語化などを目指したが、現場の負担や運用の難しさも指摘された。一部メディアでは、社員に厳しい学習を課したと報じられたが、公式に詳細を確認できる一次資料は限られている。
このような経験から、近年多くの企業が採用しているのが、部門別・段階的なアプローチである。特に海外との連携が必須となるエンジニア組織から試行的に開始し、そこで得られた知見やノウハウを蓄積しながら、徐々に全社へと展開していく手法だ。Fintech企業のマネーフォワードはその好例と言える。2021年にCTOが「エンジニア組織の公用語英語化」を宣言すると、最初の1年間はCTO室など少数のパイロットチームで先行実施した。ここで得られた成功体験と失敗談を全社で共有し、2年目以降、計画を前倒しする形で対象チームを拡大するという、漸進的なプロセスを踏んだ。このアプローチにより、一斉導入に伴う非効率な混乱を避け、各チームの準備状況に合わせた柔軟な移行が可能となった。
同社はさらに、英語を使わざるを得ない環境を意図的に創出した。例えば、日本語を話せない新卒のグローバル人材を各チームに配属したり、ベトナム出身のエンジニアをCTO室長に登用したりすることで、メンバーの英語学習へのモチベーションを高めた。同時に、社内に英語研修の専任チームを設置し、業務時間内に1日最大3時間までの学習を認めるなど、手厚いサポート体制を敷いた。こうした計画的かつ丁寧な支援と段階的アプローチが功を奏し、同社の英語化は順調に進んでいる。
また、スタートアップ企業などでは、より柔軟なチーム裁量型のハイブリッドな運用も見られる。メルカリは公式に社内公用語を定めてはいないが、多国籍なメンバー構成に応じて日本語と英語を使い分ける方針をとっている。エンジニアリング部門では主に英語が、ビジネス部門では主に日本語が使われるが、社内には双方の言語トレーニング機会が提供され、ドキュメントは可能な限り日英併記にするなど、言語による障壁を低減する工夫が凝らされている。このように、近年のトレンドは、全社一律の硬直的なルールから、現場の実情に合わせた実践的かつ部分最適な運用へとシフトしており、自社の事業内容や人材構成に合わせた戦略を採ることが成功の鍵となっている。
英語化の壁:直面する課題と乗り越えるための工夫
英語公用語化を推進するプロセスにおいて、多くの企業が共通の課題に直面する。最も顕著なのが、言語の壁によるコミュニケーションの停滞である。英語への切り替え当初、多くの日本人社員は自分の意見を表現することに苦労し、他者の発言を聞き取る余裕もなくなるため、会議が沈黙に包まれてしまうことがある。マネーフォワードの事例でも、ミーティングを英語化した直後は誰も発言しないという状況に陥り、質問や異論が出ないままプロジェクトが進行してしまった結果、情報の取りこぼしや手戻りが発生した。このようなコミュニケーション不全は、業務効率の一時的な低下にも直結する。慣れない英語での資料作成やチャット対応には時間がかかり、翻訳ツールの使用頻度も増えるため、初期段階でのスピードダウンは避けられない。
さらに、社員が抱える心理的な抵抗と不安も大きなハードルとなる。特に、長年日本語環境で働いてきたベテラン社員ほど、言語転換への拒否反応は強い。「英語では細かいニュアンスが伝わらない」「会議で内容を聞き漏らすのが怖い」といった不安は、モチベーションの低下や、表向きは従いながら実質的には日本語を使い続けるといった「サイレント抵抗」につながりかねない。メルカリの社員からも「英語を話すのは本当にストレスが大きい」という率直な声が上がっており、この心理的負担をいかに軽減するかが施策の成否を分ける。最悪の場合、急激な環境変化に適応できない社員の離職、すなわち初期段階での人材流出リスクも考慮しなければならない。
これらの複合的な課題に対し、先進企業は試行錯誤の中から効果的な解決策を見出してきた。まず、負荷の少ない領域から着手する「段階的・優先度順の英語化」が有効である。例えば、リアルタイムでの会話が求められる会議よりも、まずチャットやドキュメント作成といった非同期の読み書き業務から英語化を進めることで、社員は徐々に英語に慣れることができる。
次に、言語能力の差による情報格差を防ぐための「ドキュメント整備とツール活用」が不可欠だ。会議で聞き取れなかった部分があっても、詳細な議事録やアジェンダが英語で共有されていれば、後から内容を確認し、翻訳ツールを使って理解を補うことができる。また、定例会議で頻繁に使われるフレーズ集を作成・共有することも、発言のハードルを下げる上で効果的である。
コミュニケーションの質そのものを見直すアプローチも重要だ。ネイティブのような流暢さを求めるのではなく、シンプルな単語と短い文章で要点を明確に伝える「簡易な英語(グロービッシュ)」の使用を全社で徹底することが推奨される。マネーフォワードでは、「コミュニケーションの本質は自分の考えを正しく伝えること」というマインドセットを共有し、英語が得意な社員にも、相手に配慮して平易な表現を使うことを求めている。
そして、最も重要なのが「社員への動機付けと手厚いサポート」である。なぜ英語化が必要なのかという意義を経営層が繰り返し伝え、「英語で仕事ができるようになれば、自身の市場価値が高まり、グローバルなエンジニアとして活躍できる」といったポジティブなメッセージを発信し続けることが、社員の前向きな姿勢を引き出す。同時に、業務時間内での研修を許可したり、個々のレベルに合わせた学習プログラムを提供したりすることで、会社が本気で社員の成長をバックアップするという安心感を与えることが不可欠である。言語だけでなく、文化や習慣の違いへの理解を深める取り組みも並行して行うことで、国籍に関わらずチーム全員が協力しやすい土壌が育まれていく。
英語化がもたらす変革:組織にもたらされる多面的な効果
困難を乗り越えて英語公用語化を軌道に乗せた企業では、中長期的に見て多岐にわたるポジティブな効果が報告されている。最も直接的で大きな成果は、「グローバル人材の採用拡大と人材交流の活発化」である。英語環境が整備されることで、採用ターゲットは日本国内から全世界へと広がる。楽天では、英語化後に70以上の国と地域から人材を採用できるようになり、新規採用エンジニアの大部分を外国籍人材が占めるようになった。これにより社内のダイバーシティは飛躍的に向上し、世界中から「強烈な才能」を集めることが可能になった。日本人エンジニアにとっても、日常業務を通じてグローバル市場で通用する英語運用能力が身につき、自身のキャリア選択の幅を広げるという大きなメリットがある。
導入直後に見られた業務効率の低下も、組織が英語環境に適応するにつれて改善し、むしろ「生産性の向上」につながるケースも多い。言語が統一されることで社内ドキュメントが整理され、情報共有のロスが減少する。マネーフォワードでは、英語で議事録を残す運用を徹底した結果、コミュニケーションエラーが減り、プロジェクトの品質向上に貢献した。また、社内のナレッジが英語で蓄積されるため、新たに参加した外国籍のメンバーも迅速に情報へアクセスでき、組織全体の生産性が向上するという効果も報告されている。
もちろん、本来の目的であった「グローバル展開の加速と競争力強化」にも大きく寄与する。社内に英語という共通基盤があることで、海外拠点との連携コストが劇的に下がり、スピーディな事業展開が可能になる。海外の現地スタッフと本社メンバーが通訳を介さずに直接ディスカッションできるため、意思決定の速度と質が向上する。さらに、海外の最新技術に関するドキュメントやカンファレンスに直接アクセスしやすくなるため、エンジニア組織の技術力そのものを高め、製品やサービスの競争力強化にもつながる。
そして、英語化は単なる業務上の変化にとどまらず、「社内文化・コミュニケーションの変革」をもたらす。英語には日本語のような複雑な敬語表現が少ないため、役職や年齢に関わらずフラットな議論が活発になり、従来の根回しといった文化が薄まる傾向がある。意思決定プロセスがより論理重視になり、組織の透明性が高まるのだ。また、多様な国籍の社員が共に働く中で、互いの文化や価値観を尊重する意識が醸成され、結果として「心理的安全性」の高い職場環境が構築されることもある。ただし、実態としては完全に英語一色になるわけではなく、日本語と英語が混在するバイリンガルな運用がなされることが多い。重要なのは、どの言語を使うかということ自体よりも、メルカリが実践する「やさしい英語・やさしい日本語」のように、誰もが同じ理解に到達できるコミュニケーションを組織全体で追求する文化を育むことである。
成功と失敗の分水嶺から学ぶ、これからの言語戦略
近年成功を収めているマネーフォワードやメルカリの事例に共通するのは、英語化を単なる言語の切り替えとしてではなく、事業戦略や人材戦略と密接に結びつけ、自社の文化や状況に合わせた柔軟な方法で推進している点である。英語化そのものを目的化するのではなく、あくまで異文化を持つ人々が円滑に協働し、組織全体の競争力を高めるための「手段」として捉えている。
この視点は、経営者や専門家からも繰り返し指摘されている。メルカリの幹部は、最も大切なのは言語そのものではなく、全員が共通のミッションやカルチャーを共有することだと語る。また、楽天の英語化プロジェクトを学術的に分析したハーバード・ビジネス・スクールのツェダル・ニーリー教授は、社員をその背景によって分類し、それぞれの属性が抱える異なる課題に寄り添った支援策を講じたことが成功の鍵であったと指摘している。これは、画一的な英語研修を課すだけでは不十分であり、多様な社員一人ひとりの心理に配慮した施策設計がいかに重要であるかを示している。
こうした学びを反映し、一部の企業では「脱TOEIC」の動きも見られる。TOEICスコアという単一の指標に固執するのではなく、CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)のようなより実践的な会話能力を測る指標を導入したり、社内独自のスピーキングテストを実施したりするなど、実際の業務におけるコミュニケーション能力を重視する方向へのシフトが始まっている。
今後の展望を考えると、日本企業のグローバル化が不可逆的に進む中で、エンジニアが業務で英語を使う場面は確実に増え続けるだろう。生成AIをはじめとする技術トレンドの変化はますます速くなり、海外の最新情報に直接アクセスできる英語力は、エンジニアにとって必須のスキルとなる。政府も高度IT人材の受け入れ拡大を推進しており、企業には多様な人材が国籍を問わず活躍できる環境づくりがこれまで以上に求められる。英語公用語化への挑戦は、この大きな潮流の中で、日本企業が持続的にイノベーションを生み出し、世界の舞台で競争力を維持するための重要な一歩である。その最終目的は、単に英語が話せる組織になることではない。言語や文化の壁を乗り越え、多様な才能が協働することで、新たな価値を創造し続ける強い組織を築くことにある。その道のりは今なお進行中であり、各社の試行錯誤は、未来の日本企業の姿を形作っていくに違いない。